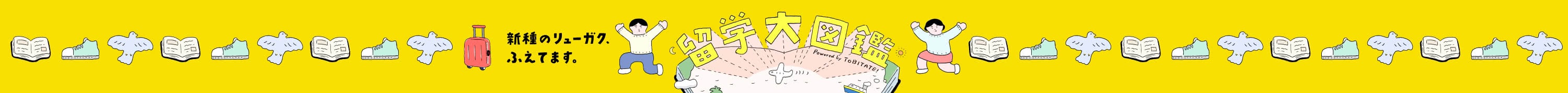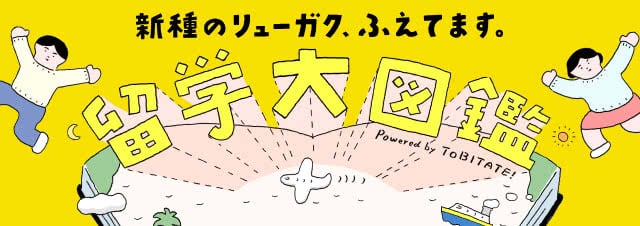大浦詩織(立命館大学/ 京都市立紫野高校 英文科)
- 留学先(所属・専攻 / 国 / 都市):
-
- Macromedia University, Media Management, Sport&Event Management, Brandcommunikation & Advertising
- ドイツ
- ミュンヘン
- 留学テーマ・分野:
- 専門留学(スポーツ、芸術、調理、技術等)
大学の協定校に希望する大学がない、もしくは、交換留学枠がそもそもないという方でも、「ドイツに留学がしたい」、「学びたい分野が決まっている」場合は、インターネットで、大学を探す際に「Free mover」というキーワードを追加して検索をかけるといいかもしれません。その大学に「Free mover」制度があるかどうかは、大学側に直接メールを送って質問しないと分からないことも多いです。それから、担当者のメールに従って書類を用意し、メールでの応募という流れになります。「Free mover」とは、母国の大学と協定を結んでいない留学の形に当たり、単位の認定がされない(大学によって異なる可能性もあります)ので、休学をした上での利用をおすすめします。また、交換留学と比べても、オリエンテーションなどのサポート体制がしっかりしていないので、全て自分で手配しなければいけないというデメリットもあります。しかし、それでも、行きたい場所がある、どうしても学びたい大学や専門学校があるという方は、ぜひ、視野に入れてみてください。語学力を一定の水準をクリアしていれば、例え専門知識がなくても、興味のある学部で自由に選べる可能性が高い留学方法です。