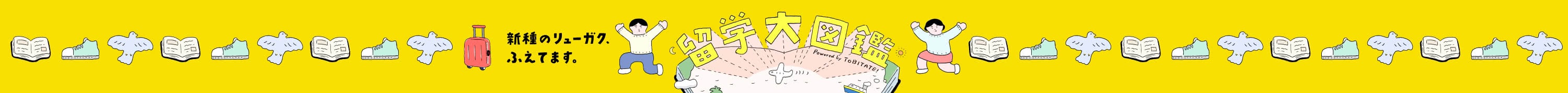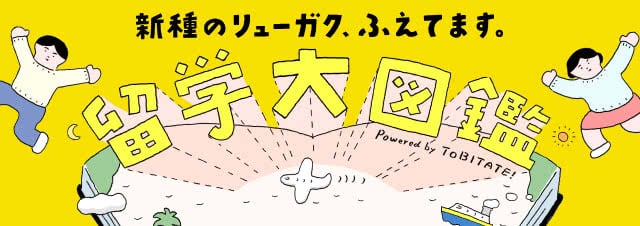留学先探しとプログラムの選択・応募
Misa( 宝仙学園高等学校共学部理数インター)
- 留学先(所属・専攻 / 国 / 都市):
-
- マサチューセッツ州立大学・コネチカット州立大学
- アメリカ合衆国
- マサチューセッツ州・コネチカット州
- 留学テーマ・分野:
- 短期留学(3か月以内、語学・ボランティアなど各種研修含む)・専門留学(スポーツ、芸術、調理、技術等)
最初はどうやって探したら自分にピッタリなプログラムが出てくるかが全くわからず、なんとなくキーワードで探していました。親もプログラムを選ぶ際、サポートしてくれたので、最終的には沢山の選択肢から選び出す形となりました。 結局は複数のプログラム・大学に応募書類を提出し全てacceptされたので、その中からもっとも行きたいと思っていた2つのプログラムに参加することになりました。 応募に関しては、まるでアメリカの大学に進学するときのような書類を提出する必要がありました。それも全てプレカレッジの一貫だったのかもしれません。 まずはそのプログラムを希望する理由を書いたエッセイ(自己推薦書)そして学校の成績表、さらにRecommendation Letterという先生に書いてもらう推薦書も準備しました。大変でしたが、沢山の人の協力があったので全てやりきることができました。
続きを見る