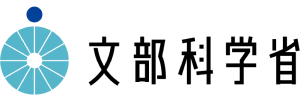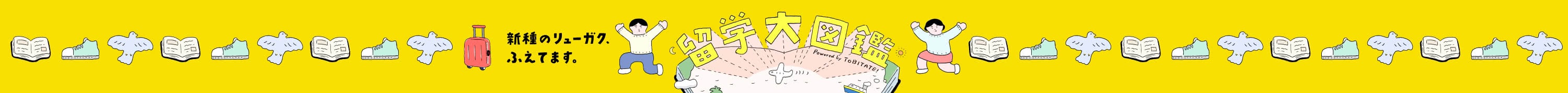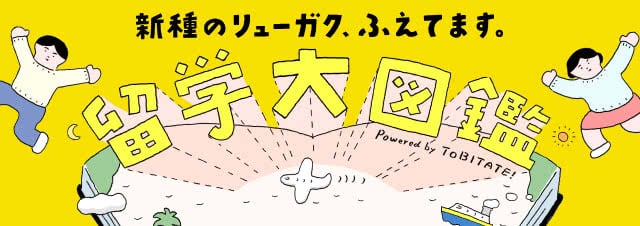かっちゃん(慶應義塾大学/ 静岡県立清水東高等学校)
- 留学先(所属・専攻 / 国 / 都市):
-
- Projects Abroad
- 南アフリカ・イタリア
- レッジョカラブリア・ケープタウン
- 留学テーマ・分野:
- 海外インターンシップ
私はこのボランティアやインターンを通して、ただの支援で終わってしまう悔しさを痛感しました。最初のイタリアではタイトルにもある「持続可能な支援」ではなくただの支援で終わってしまっていたことに気づきました。活動中はそのことに気づくのが難しく、お別れの時に気づくことが多かったため、悔しさとともに涙を流してしまいました。なのでこれから国際協力の分野に進みたい人や貧困問題などをテーマに勉強している人はこの視点を忘れず、取り組んでほしいと思います。
現在、大学のゼミでは教育、コミュニケーションを共通テーマに、5つのプロジェクトの中でコンゴプロジェクトに所属しています。ここではコンゴ民との「協働」を通じた持続可能な発展と、その先にある両国の発展を目標に、異文化である現地での実践活動を通して、「国際的な域学連携のモデルケース」の実現を目指しています。個人的には留学で見出した”持続可能な支援”のもと現地の学生や主婦たちに、収益面での手助けをすることで、可能性と選択肢を広げ「次世代の若者が夢を追い続けられる社会」を目指しながら活動をしています。この留学をこの活動に生かしたいと思っています。