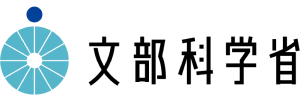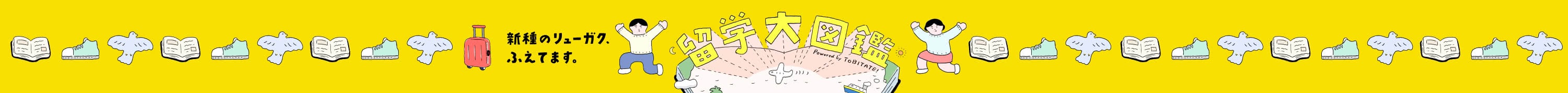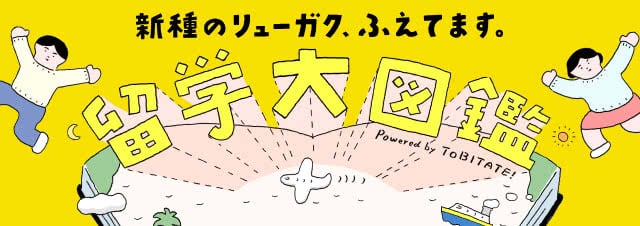留学内容
①現地医療現場の視察
医療プログラムの一環として、病院やクリニックを訪問し、現地医療従事者の業務を視察した。特に、産科を中心に、資源や設備が限られた環境でどのように患者と向き合っているのか、効率的な医療提供の工夫や課題を観察した。医療従事者へのインタビューを通じて、異文化環境で働く際の具体的な心構えや課題も探った。
②語学学習とコミュニケーションの実践
語学授業を受講し、英語のスピーキング力を高めるとともに、スワヒリ語の基本フレーズを学んだ。これにより、現地の患者や医療スタッフと直接コミュニケーションを取り、文化や価値観の違いを理解する力を養うことができた。将来の国際医療活動に必要な言語スキルを体験した。
③ヒアリング
この地域で働く中で、最も大きな課題は何か?
困難な状況下で、働き続ける理由は何か?
なぜ仕事場として、この地域を選んだのか?
医療現場で、医者や看護師にヒアリングを行い、活動中は現地の観察やインタビューで得た情報を日記や記録としてまとめた。視察した医療現場の課題や、異文化環境での働き方について感じたことを記録し、留学後に問いの答えを整理する際のデータとして、文化祭で発表した。