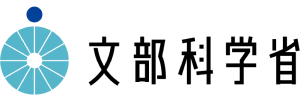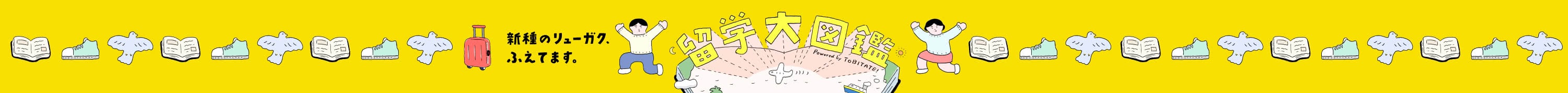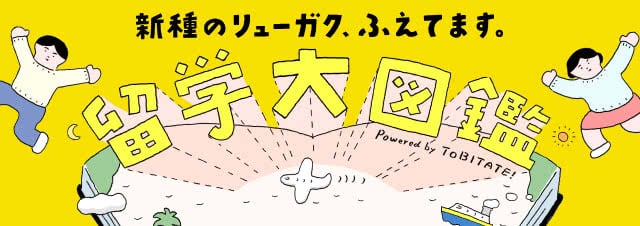留学内容
「日本とインドネシアのビジネスにおける架け橋に」をテーマに、インドネシア大学で8か月間インドネシア語を学び、その後、現地の財閥系企業で4か月間インターンシップを行った。留学を通じて、インドネシアの中間層のライフスタイルや、日系企業がどのように同国へ進出しているのかについて理解を深めた。
大学留学中は比較的所得水準の低い地域(kampung)に身を置き、地域の子どもたちを対象に日本語教室を開講した。週2回、日本語や日本文化を教える活動を通して、都市部のkampungに住む人々の生活様式を直接学ぶことができた。
一方、インターンシップでは、勤務先であるSinar Mas Land社が開発するBSD Cityに滞在した。そこで中間層以上の人々の暮らしを体感するとともに、インドネシア市場において日系企業が中間層を中心とした顧客層にどのようにアプローチしているのかを、実際のビジネス現場で学んだ。